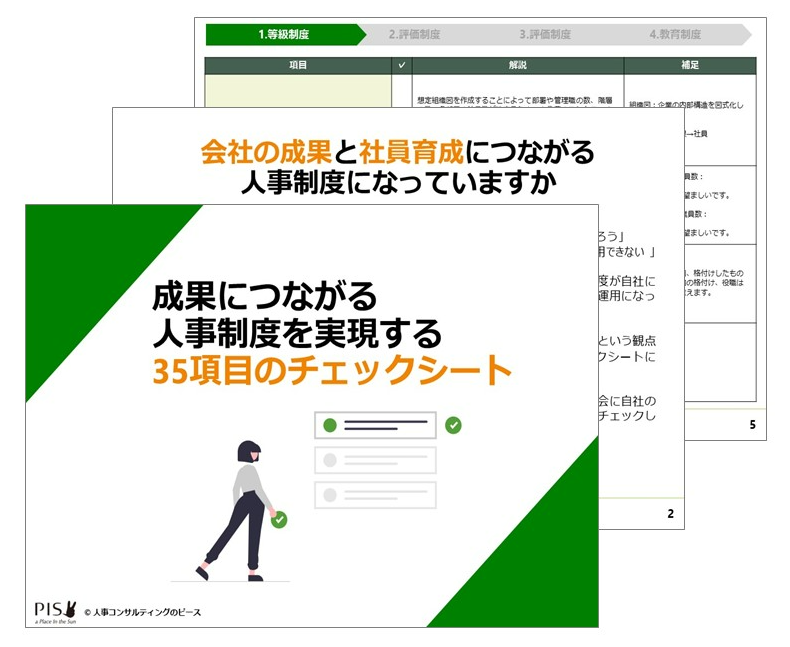会社は人が入れ替わる。本当にたくさんの人が入れ替わるだから、出会いと別れは必然だ。
だがもちろん、そう言いつつも誰にとっても別れはそれほど良いものではない。
特に、上司をやったことのある方であれば、有能な部下が突然、「済みません、ちょっとお話があるのですが……」と言われ、少し嫌な予感がし、
別室にて、「実は、……来月末で退職させていただきたいのです」といわれた瞬間の動揺は、筆舌に尽くしがたいものがあるのではないだろうか。
その瞬間、頭のなかでは
「この人がやめると……現場が回らないのでは」
「引き継ぎがきっついな―」
「何が問題だったのだろう?原因はオレかな……」
「何もこんな時期に辞めなくても」
と、怒りとも、寂しさとも、諦めともつかない感情が芽生えるだろう。
さて、ここからあなたには三つの選択肢がある。
1.一生懸命引き止める
2.気持ちよく送り出してあげる
3.口汚く罵る。
どの選択肢を選択するだろうか?
まず、3.の選択肢だ。
当たり前だが労働者には職業選択の自由がある上、一ヶ月前に予告すれば辞められる雇用契約がある。もちろん会社としては三ヶ月前には言ってほしい、と思うだろうが、そんなにできた人ばかりではない。
ときには忙しい時に、いや、忙しい時だからこそ辞めたい、という人も少なくないだろう。だから、あまりの配慮の無さに、思わず口汚く罵ってしまった、との話も実はよく聞く。
ただ、そんなことをやっても当然、当人の辞める決心は揺らがない。むしろ当人は「ああ、やっぱり辞めて正解だった」との確信を深めるだけである。
とすると、選択肢は1.もしくは2.つまり、「引き止める」か「引き止めずに気持ちよく送り出す」の二通りが選択肢として存在する。
有能な人は引き止めるべきなのか?それとも、気持ちよく送り出すべきなのか?
判断に迷うだろう。
さて、結論から言うと「辞めていく有能な社員」を引き止めることはやめたほうが良い。辞めたい、と言ってきた人は常に気持ちよく送り出してあげよう。
理由は以下の通りだ。
1.「辞めたい」と上司に言ってきた人の心は、もう固まっている
上司に「辞めたい」と言うのは、社員にとっては極大のリスクである。なにせ、会社への忠義や愛社精神を根本から否定する行為なのだ。
とすれば、「辞めたい」というまでには相当の葛藤があったはずである。その葛藤を乗り越えてまで、上司に言うことを決心したのだから、かなり堅い決心と言っても良いだろう。
だから、ほとんどの場合説得は時間の無駄である。
2.引き止めに成功したとしても、他の社員の不満は高まる
もしかしたらその社員を引き止めるためにあなたは様々な条件を出すかもしれない。「給与」「仕事内容」「権限」など、条件面の不満は多種多様である。
だが、「辞めたい」という最後のカードにたいして妥協すれば、結局のところ「辞めたいといったもの勝ち」になってしまうことは否めない。
また、引き止められた社員は事あるたびに、「自分は上から引き止められた人材である」と吹聴して回るだろう。
その時に他の社員はどう思うだろうか。
「その人がいないと回らない仕事」に見えても、殆どの場合は他の人が代替できるのだ。他の社員への配慮も踏まえ、引き止めることはデメリットが大きい。
3.また同じことが起きる
なぜその社員がやめようと思ったのか、その根本的な原因が解決しない限り、また同じことが起きることは間違いない。例えば人間関係、職場環境、評価、プライベートの状況……。
そして、上はほとんどの場合、「我慢してくれ」と引き止めに成功しても「原因」をその一人の人間のために解決したりはしない。
だから、結局のところまた同じことが起きる。引き止めに応じても、その社員は半年後にまた「やめたいです」と言ってくるだろう。そういうものである。
要するに、「やめたいです」と言われてから、その社員のために動くことは、はっきり言って無駄である。
社員をやめさせたくないのなら、普段からひとりひとりの表情に気を配り、彼らの考えていることを把握し続けなければならない。引き止めるのではなく、「辞めたい」と言わせないことのほうが遥かに重要なのだ。
やめていく有能な社員を、「裏切り者」や「アイツは無能だった」と後ろ指を指す会社もある。
だが、大なり小なり、真の理由は皆わかっている。無駄に引き止めたり、口汚く罵ることはご法度だ。
では、上司は「やめていく有能な社員」に対してどう考えたら良いのだろうか。辛い別れではなく、旅立ちを喜んであげられる方法はあるのだろうか。
1つは、やめた人物から外部へつながる窓ができることだ。会社をやめたとしても、その人物とのつながりは消えるわけではない。
何かの折に、仕事や人を紹介してくれるかもしれないし、別の会社の状況を知ることで新しいアイデアを得ることが出来るかもしれない。
もう1つは、やめた人物を通じて企業のブランディングが出来ることだ。
マッキンゼーやGoogleは、そこに在籍していたOBが活躍していることで有名だが、やめた人の評判が良ければ、その元企業の良い評判にもなる。
辞める人の前途を祝してあげることで、会社は外部のネットワークを強化できる。悪いことばかりではないのだから、喜んで新しいチャレンジを応援してあげよう。