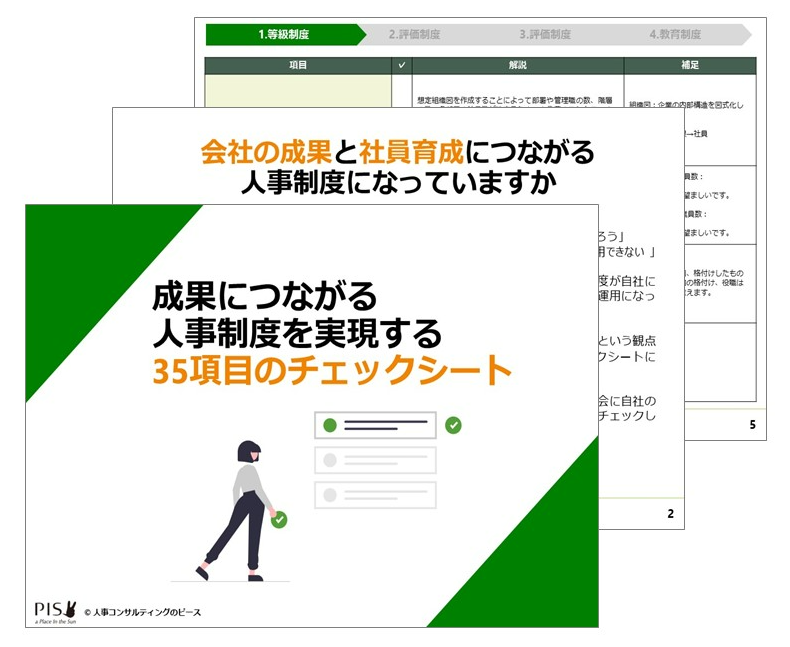インフレが加速する中で、ベースアップを実施する企業が増えてきている。これから検討している経営者も多いのではないだろうか。
そこで、2023年7月現在のベースアップ動向について、データをもとに確認してみたい。
※ベースアップとは、全社員の基本給を一律に引き上げる賃上げのことをいう。
現金給与総額の推移
厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査(従業員5人以上)の結果を表にまとめると、以下のようになる。
※ 7月12日時点で5月分は速報値、6月分は未発表
※ 一般労働者:常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。
※ 現金給与総額:基本給、残業代、ボーナスなどを含む給与
※ 単位:円
| 年月日 | 一般労働者の 現金給与総額 (名目賃金) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2023年5月 | 368,417 | 103.0% |
| 2023年4月 | 369,468 | 101.2% |
| 2023年3月 | 383,016 | 102.1% |
| 2023年2月 | 352,823 | 101.3% |
| 2023年1月 | 360,989 | 101.4% |
| 2022年12月 | 782,495 | 104.6% |
| 2022年11月 | 375,392 | 102.1% |
| 2022年10月 | 357,120 | 101.9% |
| 2022年9月 | 357,495 | 102.5% |
| 2022年8月 | 362,821 | 101.9% |
| 2022年7月 | 499,779 | 101.5% |
| 2022年6月 | 608,627 | 102.6% |
| 2022年5月 | 357,658 | 101.3% |
| 2022年4月 | 365,254 | 101.8% |
| 2022年3月 | 375,255 | – |
| 2022年2月 | 348,256 | – |
| 2022年1月 | 356,142 | – |
| 2021年12月 | 748,421 | – |
| 2021年11月 | 367,758 | – |
| 2021年10月 | 350,609 | – |
| 2021年9月 | 348,787 | – |
| 2021年8月 | 356,007 | – |
| 2021年7月 | 492,211 | – |
| 2021年6月 | 593,271 | – |
| 2021年5月 | 353,189 | – |
| 2021年4月 | 358,768 | – |
4月~6月にかけて賃金改定を行う会社が多いと想定されるので、2023年4月、5月のデータに注目するとよいだろう。
2023年4月の一般労働者の現金給与総額は、369,468円で前年同月比で1.2%の上昇に留まっている。3月決算、賃金改定が5月からという会社が多いのか、ベースアップ率は小さい。
2023年5月は、368,417円で前年同月比で3.0%の上昇となっており、ベースアップが本格的に始まっている様子が伺える。
※毎年6月、12月の金額が大きいが、これはボーナスの影響。
賃金改定を6月以降に行う会社もあるため、まだまだ全体像が確認できない部分もあるが、2023年度全体としては3%+αぐらいのベースアップになりそうだ。4%台もあり得る。
2022年度(2022年4月~2023年3月)は平均すると、2.1%の賃上げをしている。2023年度の賃上げ率が平均で3%だと仮定すると、2年間で2% × 3% ≒ 5%の賃上げを行うことになる。
これが全体の動向だ。他社のモノマネをするという意味では、この2%~3%を意識しておけばよいだろう。
実質賃金の推移
では、自社も2年間で5%のベースアップを行えばよいかというと、そうではない。社員の生活を考えるのであれば、物価上昇を考慮しないといけない。
実際に支給している賃金を「名目賃金」と呼ぶ。対して、物価上昇分を考慮した賃金を「実質賃金」と呼ぶ。社員の幸せを考えるのであれば、実質賃金を上げなければいけない。
実質賃金は、名目賃金 / 物価上昇で計算される。
例えば、賃金を30万円から10%上げて、33万円にしたとする。表面的には3万円の昇給だ。
一方、物価も10%上がったとする。実質賃金は33万円/1.1=30万円となり、実質的には1円も昇給していないことになる。
では、実質賃金はどうなっているのだろうか。
消費者物価指数(CPI)をもとに実質賃金をまとめると以下のようになる。
※消費者物価指数:消費者が購入するモノ・サービスを対象とした価格を、集計した指数。実質賃金を計算する場合は、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を用いる。
※政府機関が発表する実質賃金は、様々な統計処理が施されており、以下の表の数字とは少し異なるが微差である。
| 年月日 | 名目賃金 | 前年同月比 | 消費者物価指数 | 実質賃金 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | 368,417 | 103.0% | 106 | 347,563 | 99.2% |
| 2023年4月 | 369,468 | 101.2% | 106 | 348,555 | 97.1% |
| 2023年3月 | 383,016 | 102.1% | 105.2 | 364,084 | 98.3% |
| 2023年2月 | 352,823 | 101.3% | 104.7 | 336,985 | 97.5% |
| 2023年1月 | 360,989 | 101.4% | 105.5 | 342,170 | 96.5% |
| 2022年12月 | 782,495 | 104.6% | 104.9 | 745,944 | 99.7% |
| 2022年11月 | 375,392 | 102.1% | 104.6 | 358,883 | 97.7% |
| 2022年10月 | 357,120 | 101.9% | 104.3 | 342,397 | 97.5% |
| 2022年9月 | 357,495 | 102.5% | 103.6 | 345,072 | 98.7% |
| 2022年8月 | 362,821 | 101.9% | 103.2 | 351,571 | 98.5% |
| 2022年7月 | 499,779 | 101.5% | 102.7 | 486,640 | 98.7% |
| 2022年6月 | 608,627 | 102.6% | 102.1 | 596,109 | 99.9% |
| 2022年5月 | 357,658 | 101.3% | 102.1 | 350,302 | 98.6% |
| 2022年4月 | 365,254 | 101.8% | 101.8 | 358,796 | 99.1% |
| 2022年3月 | 375,255 | – | 101.3 | 370,439 | – |
| 2022年2月 | 348,256 | – | 100.8 | 345,492 | – |
| 2022年1月 | 356,142 | – | 100.4 | 354,723 | – |
| 2021年12月 | 748,421 | – | 100 | 748,421 | – |
| 2021年11月 | 367,758 | – | 100.1 | 367,391 | – |
| 2021年10月 | 350,609 | – | 99.8 | 351,312 | – |
| 2021年9月 | 348,787 | – | 99.8 | 349,486 | – |
| 2021年8月 | 356,007 | – | 99.7 | 357,078 | – |
| 2021年7月 | 492,211 | – | 99.8 | 493,197 | – |
| 2021年6月 | 593,271 | – | 99.4 | 596,852 | – |
| 2021年5月 | 353,189 | – | 99.4 | 355,321 | – |
| 2021年4月 | 358,768 | – | 99.1 | 362,026 | – |
表にあるように、実質賃金は、2022年4月からずっと13ヵ月連続でマイナスとなっている。
今回はパートタイマーのデータを入れていないが、パートタイマーを含む全体で見ても実質賃金は13ヵ月連続でマイナスになっている。
物価上昇を考慮すると、今の賃上げペースである、2022年度が2%、2023年度が3%、2年間で5%では不十分であることがわかる。
できれば物価上昇分を吸収するぐらいの賃上げを意識したいところだ。
消費者物価指数の推移をみると、デフレが終わり、インフレが始まったのは2022年1月頃と判断することができる。(2021年代は、消費者物価指数が100を割り込んでおり、まだデフレだ)
2023年5月の消費者物価指数が106ということは、1年半で物価が6%上昇したことになるので、5%の賃上げで足りないのは当然である。
2年で6%以上の賃上げをしてはじめて、実質賃金が上がったと言える。去年2%上げた会社なら、今年は4%ぐらいを意識しないといけないだろう。
去年賃上げをしなかった会社では、今年6%ぐらいを意識しないといけない。
こう考えると、利益率にもよるが、商品・サービス価格を最低でも10%ぐらいは上げないといけないことになる。
商品・サービス価格の値上げに成功した会社は、速やかに賃上げを行って欲しい。